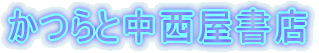清水かつらは、大正5年(1916年)青年会館英語学校を退学し、東京市神田区表神田2番地(現在の靖国通りの駿河台下交差点付近)にあつた玩具と書籍の合資会社中西屋書店出版部へ入社した。
中西屋書店は革新的な絵本の発行でも知られていたが、唐物や用品類などの舶来品も扱っていた。店先の窓ガラスの中に洋書を美しく並べていた。
武田勝彦著「漱石の東京Ⅱ」には、明治42年頃、本郷に住んでいた夏目漱石が市内電車を駿河台下で降り、このショーウィンドーを眺めた様子が小説「門」に記されていると、紹介されている。中西屋書店では洋書の販売のほかにも絵本の出版を行っていた。
中西屋書店では、少年・少女向けの雑誌を刊行するため「小学新報社」を創設したので、かつらは鹿島鳴秋とともに少女雑誌の編集に携わることになる。雑誌の編集はかつらの好きな道であり、文学的才能を発揮出来る格好の場所であったから、大いに発奮し鹿島鳴秋とともに少女雑誌「少女号」や「幼女号」「小学画報」を編集、発行した。「少女号」の編集長兼発行人は鹿島鳴秋であった。
鹿島鳴秋は、明治24年(1891年)深川区東大工町(現白河二丁目)に生まれた。佐太郎は本名である。東大工町は小名木川をはさんで、かつらの出生地と隣り合っていた。
苦労して夜間商業学校を卒業し、外国商社に勤めたこともあるが、明治43年、処女作童話「塔の姫」が毎日電報(現在の毎日新聞の前身)に当選し、その選者であった巌谷小波(いわやさざなみ)に師事して児童文学にすすむ。明治45年、竹貫佳水、蘆谷盧村、山内秋生らの少年文学研究会同人となった。大正の末、北原白秋らの童謡詩人の会の会員となり、童話作家協会の創立に参加した。大正5年(1916年)から丸善に勤務していた。
もう一人の編集者として井口長二がいた。井口長二はのちに剣豪作家となる山手樹一郎の本名である。子息が直木賞候補作家の井口朝生である。
山手樹一郎は、明治32年(1899年)栃木県黒磯市に生まれ、東京の明治中学第1回卒業生。早稲田大学文学部への進学を諦め、小学新報社へ就職した。「少女号」では、「帰らぬ少女」「青い窓」「お父さんの靴下」などの少女小説を執筆していたが、小説家への道は断ちがたく大正14年に退社している。
当初、小学新報社は中渋谷にあり、大正9年頃に神田駿河台南甲賀町に移転している。お茶の水駅から駿河台下に向かうと左手に主婦の友ビルがあり、その裏辺り、現在NTT駿河台の所である。周りの風景は全く変わっているが、近くの太田姫稲荷神社は古色蒼然たる姿で残っている。
神田小川町は江戸時代、鷹匠町と呼ばれていたが、この辺りに土屋采女正の上屋敷があった。かつらの先祖は土屋采女正に仕えていたから、江戸の歴史に詳しいかつらがその事を知らない筈はなく、全くの偶然とも言えないだろう。
当時、神田須田町は、各方面からの路面電車が集結する交通の要衝であった。須田町から九段下に至る靖国通りが東京のメインストリートであった。現在の交通博物館の所に甲武電車(中央線)の万世橋駅があり、赤レンガが当時の面影を残している。
大正7年、鈴木三重吉により童話雑誌「赤い鳥」が創刊された。また、児童雑誌では「幼年の友」「少女の友」や浜田広介による「良友」「子供の友」などが発売されていた。「赤い鳥」に刺激され大正八年には、「小学男性」「小学女性」や野口雨情らが執筆した「金の船」などが発刊された。更に年末には、子供向けの画期的な絵本「コドモノクニ」が発刊され、北原白秋、野口雨情、西條八十、中山晋平、弘田龍太郎らが執筆している。このように大正時代は童謡の最盛期であり、ふと口ずさんで出てくる童謡のほとんどはこの時代に作られている。
鈴木三重吉は、「赤い鳥」以外の雑誌は模倣にすぎないと非難しており、野口雨情、与謝野晶子、鹿島鳴秋そして清水かつらなどの人々を、童謡を侮辱している作者として指摘している。しかし、小学新報社の「小学画報」は「赤い鳥」に続いて大正9年に創刊されたが、「少女号」はそれより早く大正5年に発刊されていた。「少女号」は少年少女雑誌の型を創り、後に続いた多くの子供雑誌に先鞭をつけたものとして評価されよう。
テレビやラジオのない時代、「少女号」で全国に紹介された「叱られて」や「靴が鳴る」「あした」「雀の学校」などが、やがて演奏会でも演奏され、レコードとなって子供達に愛唱された。かつらの目指したものは、「赤い鳥」のような芸術性の高い高尚な童謡ではなく、子供達の喜びや悲しみを素直に歌った、自然に子供達の心にとけこんだ童謡であった。
河原和枝著中公新書「子ども観の近代」の中で大正10年に都市と農村の子どもの読み物を調査したデータがあるが、東京で多く読まれていた本は「譚海(たんかい)」「少年世界」「少女世界」などであるが、女子だけに限れば「少女号」が6位で「赤い鳥」は10位であった。農村部では、「少女号」も「赤い鳥」もあまり読まれていなかった。
「少女号」も「赤い鳥」も都会を中心に販売されていたが、「少女号」の清水かつらの詩は都会的であったのに対し、「赤い鳥」の野口雨情は地方の子供たちにも愛される詩でなければいけないと考えていた。
小学新報社では、童話や童謡の作者への稿料、挿絵画家への画料が十分まかなえなかったことから、編集者自ら原稿を書いていた。編集者が筆をとることは、ここに限らず当時の雑誌社ではごく当たり前のことだった。毎号、原稿を補う意味で、童謡、童話、小説、伝記、物語などを次々に発表し人気を博した。
「少女号」などの雑誌に共鳴して参加した執筆陣は多彩であった。劇作家で大正13年に築地小劇場を創設した小山内薫は、映画や小説の分野で活躍していた。児童文学の小川未明、弘田龍太郎の隣に住んでいたサトウ・ハチローも児童文学作家であるが、大正8年頃は西條八十に師事していた。詩人の佐藤惣之助や白鳥省吾、野口雨情。画家でもあった中西悟堂、室生犀星、蘆谷盧村など。作家の高垣眸や長尾豊、伊藤孝之、布目敏行、池部鈞らが執筆に協力していた。
「小学画報」や「少女号」で挿絵を書いていた画家のひとりに本田庄太郎がいる。本田庄太郎は明治26年(1893年)浜松市平田(なめた)町に生まれた。いかにも大正時代をほうふつさせる「少女号」の表紙や口絵を毎月書いていた。本田庄太郎の絵は毎号読者に評判であった。本田庄太郎の人柄どおり、彼の挿絵に描かれる人物は楽天的で素朴な農村風のものも多かった。本田庄太郎は成増の近くに住んでいた。いつもはかまをはいており、丸顔で小柄な人だった。かつらとは大変親しく一緒に酒を飲むことが多かった。
同じ挿絵画家に池内茱萸、本名伊丹万作がいた。明治33年、松山市の生まれで中学校卒業後、上京して鉄道院に勤め、かたわら洋画を学んでいた。かつらとも親しく、退職後挿絵を書いていたが、シナリオも書くようになり映画監督に転身した。俳優で監督であった伊丹十三の父である。ほかに、山口將吉郎のような歴史画家で武者絵を得意とした人や日本童画の基礎を築いた武井武雄などがいた。
神田駿河台南甲賀町にあった小学新報社は、大正14年(1925年)神田錦町3丁目に移っている。現在の東京電機大学の西側である。更に、神田小川町に移転、靖国通りの密集したスポーツ用品店の裏通りであった。大正15年(1926年)、中西屋が丸善株式会社に併合されたため、「小学新報社」は独立して「新報社」に改称、丸善に移った鹿島鳴秋が運営していた。事務所も小石川区原町(文京区)、麹町区有楽町(千代田区)、中野へと移転した。
かつらは、大正15年の11月号から「小学画報」の編集も担当することになった。
「小学画報」は「少女号」読者の弟や妹を対象に、おはなしや童謡、いろいろ変わった面白い遊戯のお話や手工遊びを載せていきたいと、編集後記に書いている。 新報社は関東大震災による打撃で経営不振となり、編集兼発行人であった鹿島鳴秋は、浦和の家も手放すことになった。それでも建て直すことが出来ず、山手樹一郎が退社したこともあって、経営は人手にわたってしまった。しかし、かつらは童謡詩人として、児童小説の作家として「小学画報」などに寄稿していた。
昭和2年(1927年)、かつらは新報社を退社。この後、雑誌の発行は講談社や小学館、博文館などが主流となる。