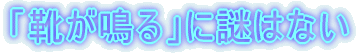「靴が鳴る」 作詞 清水かつら 作曲 弘田龍太郎
お手(てて)つないで 野道をゆけば
みんな可愛(かわ)い 小鳥になって
唄をうたえば 靴が鳴る
晴れたみ空に 靴が鳴る
草のそよ風 足なみかるく
みんな可愛い 蝶ちょになって
丘を越えれば 靴が鳴る
晴れたみ空に 靴が鳴る
花をつんでは おつむにさせば
みんな可愛い うさぎになって
はねて踊れば 靴が鳴る
晴れたみ空に 靴が鳴る
「靴が鳴る」は、かつらの作品の中でも最も親しまれた歌ではないだろうか。ピカピカに光る靴、まだ下駄や草履の方が多かった時代、ズックの靴でも珍しいのに、新品の革靴を履いた気持ちは天にも昇る思いではなかったろうか。キュッキュッと鳴るような靴を履いていたのは、校長先生や村の有力者だけではなかったろうか。
「靴が鳴る」はかつらが幼い頃訪れた白子や成増の風景を題材にしていると、白子や成増の人達は信じていた。かつらが白子村を訪ねていた頃、白子小学校や赤塚小学校は既に開校し、生徒たちは土ぼこりの道を通って、たんぼの畦道を通って、元気良く学校へ通っていた。
〝入学式が待ち遠しい新入生が、新しい靴を履いて歩き回っている嬉しそうな楽しそうな声が聞こえてくるような歌〟であると思っていた。
いつでも革靴が買えるような富裕な家ではなく、かといって無理して買った革靴でもない、ようやく靴を買えるようになった中流家庭の姿は、仕事に没頭していた父と母のいない生活から、第二の母を迎えてやっと安堵の日々を迎えたかつらの人生でもあったろう。
大正八年、「少女号」に発表された時は二番迄であった。「靴が鳴る」が歌い継がれて二十年後、昭和十二年に日本蓄音器商会から発行された「日本童謡全集」には、一番と二番の間にもう一番加えられている。
「日本童謡全集」(日本蓄音器商会刊)の中で、かつらは次のようにも述べている。
「靴が鳴る」は、仲よく皆さんが野あそびにゆく、可愛い姿をうたったものですが、それはまた昔の、私の姿でもあります。東京に生まれて育った私にも、野あそびの楽しみはありました。私の子供の頃は、東京もまだずっとせまく、郊外の近かったことが、なつかしく思い出されます。小さな足でもあるいてゆける町はずれには、小川がさらさらながれて、茅ぶきのお百姓家の、そこはもう田や畑が、ひろびろと眺められました。水車の唄もきかれました。そのけしきがうれしく、私たちはみんなで、よくあそびにいったものです。そうです、「靴が鳴る」の歌そのままに、お手々つないで。
手をつなげば、私たちはまた、れんげの花にひらいて、お月さまの唄にまるく、いつでも、どこででも、仲よくあそんだものでした。その手つなぎの手のぬくみは、うれしく、今もなお私の手に感じられて、遠く近く別れたお友だちのことが、なつかしくおもわれます。お手々つないで。それはまた、心をつなぐことであります。力をあわせることでもあります。
「靴が鳴る」が、大正童謡を代表するほどの名曲になったのも、弘田先生との手つなぎがよく、この童謡を生かしたのだと、私は信じます。これからもなお私は、この心で作曲の諸先生とよい童謡をたくさんに、うたいあげたいと思います。
皆さんも、お手々つないで行きましょう。皆さんが足なみそろえてゆく道は明るく、コドモニッポンの空は、いつも青空です。さあ、お手々つないで進みましょう。きょうも、仲よくあしたも。
かつらが厳しくも優しく教えを受けていた母と突然別れねばならなかった寂しさ、母と手つなぎの出来なかった悔しさが、童謡の中に表現されている。手の届かなかった母の手のぬくもりを求める気持ちが、かつらの胸中から消え去ることはなかった。
「靴が鳴る」は、新しい靴を履いたときの躍動感と心と心の手をつなぐ喜びを歌った、現実から別世界への転生の歌とも言える。
かつらに聞こえた靴の音は、皮靴の音でもなく、砂利を踏みしめて歩く音でもなかった。靴を履いた嬉しさに、はずむ胸の音、浮かれる心の音であった。
かつらは、楽譜集の中で、「『靴が鳴る』はたのしい遠足の様子を歌ったもので、色々な遊戯をしながら歌って見ましょう」と言っている。
新しい靴で遠足に行く楽しさを歌った「靴が鳴る」。本郷の私立習性尋常高等小学校に入学したかつらが東京の郊外へ遠足に行くと言っても、それほど遠いところではなかったろう。明治時代末期に東京の郊外と言えば〝東京市〟の周辺部であり、駒込や日暮里、新宿なども田や畑が残っていた。かつらは駒込の吉祥寺や、今は六義園になっている岩崎家の別邸などへ遠足で行ったのではなかろうか。新しい靴を履いて、田や畑の道を行く遠足。靴は必ずしも革靴ではなかったかも知れない、ズックの靴でも、靴は鳴ったのである。それは、〝腕が鳴る〟の〝鳴る〟と同じ意味で、喜び勇んで出掛ける遠足に心も弾む思いであった。
「靴が鳴る」の解釈は各人各様であるが、中にはとんでもない見方をしている人もいる。祥伝社発行の「童謡の秘密」で、著者の合田道人氏が「赤い鳥」や「少女号」は中流家庭の子弟を対象にしていたというところまでは良いのだが、中流家庭を築いたものは戦争であり、第一次大戦終了の翌年に発表された「靴が鳴る」は戦争を賛美していると言う。その著書からの抜粋。
清水は人々の命を奪った憎き戦争も、勝つことにより国が富み、思いがけない産物、童謡を生み育てたことに対し、一種の喜びすら感じていた。
この歌の靴の音、それは一般人には遠い存在である革靴が鳴っているのではなかった。この靴の音は、戦場へと向かう軍靴の音だったのである。
兵士たちが足並みを揃えながら、〝ザッザッザッザッ〟と行進し、戦地へ赴く靴の音。それこそが、「靴が鳴る」だった。
(中略)
全員でひとつになって、つまり
♪おてて つないで・・・・
軍靴を鳴らしながら敵陣に向かうことによって、日本はまた大きく成長して行ったのである。
(中略)
♪晴れたみ空に・・・・
とは、神々などに対して敬いの気持ちを込めるときに使われる言葉なのだ。日本の神とは、本質的に天皇をさすことになる。御空、つまり天皇陛下のために、
♪靴が鳴る・・・・
日本人は、戦場へとはせ参じたので。天皇陛下万歳と叫びながら・・・・。そして勝利により人々の生活に潤いが満ちてくる。それは、子供たちへの教育の関心度の高まりでもあった。
新しき暮らしの扉を開くうれしさで心が弾む。胸が高鳴る。だからこそ、そのために靴は鳴るのだ。軍靴が鳴るからこそ胸が高鳴るのだ。そんな思いをこの歌は根底に秘めていたのである。
このような解釈を紹介することさえ嫌悪感を覚えるのであるが、どう解釈するかは本人次第なので自由ではあるが、このような解釈を信ずる人がいないとも限らないので、あえて反論を記述したいと思う。
「童謡の秘密」では、更に続いており、後から追加された二番にあった
♪みんな可愛い 蝶々になって
についても、この〝蝶々〟は飛行機を意味していると言ったり、
♪丘を越えれば・・・・
とは一線を越えること、つまり軍靴を鳴らして侵略することだと解説する。二番の追加された時期が昭和十二年で日中戦争が始まった年だったと言っても、余りにも飛躍したこじつけの解釈としか思えない。
戦時中には防空童謡や軍歌さえも作っていたかつらであったが、この時期に戦争を賛美するような意図はまったく見られない。かつらにその意思があったのなら「靴が鳴る」以外にも似たような作品があって然るべきである。ましてや、かつらが〝戦争が童謡を生み育てたことに対し、一種の喜びすら感じていた〟という根拠はなく、著者の恣意のある無神経な意見に過ぎず、かつらを侮辱するものである。
軍隊が戦地へ行くのに〝お手々つないで〟行くのだろうか。〝御空(みそら)〟は、空の敬称で天皇は〝御門(みかど)〟ではないか。〝蝶々〟が飛行機と言うのもいただけない。今にも落ちそうで、飛行機なら〝トンボ〟の方が適切である。国境が丘とは限らない、川だってあるのだ。軍靴を履いて前線に送られた兵士の胸は高鳴っていたのだろうか、お国のためとは思っても不安もあったのではないだろうか。侵略に胸が高鳴っていたのは、軍靴を履かなくても良かった人たちではなかったろうか。
「靴が鳴る」の歌詞の中には野道や可愛い小鳥、花やおつむも出てくるが、これらは何を表現しているのだろう。
「靴が鳴る」が発表された昭和八年は戦勝景気に沸いていた時期で、もし戦争を賛美したいのなら、なにも童謡の中に織り込まなくとも、ストレートに表現すれば良かったのではないか。むしろ、かつらは戦勝気分に浮かれる社会に対し、みんな仲良く争いのない世界を「靴が鳴る」の中に表現し、警鐘していたのではないだろうか。結局、「童謡の謎Ⅰ~Ⅲ」の続編として出版された「童謡の秘密」では、少なくとも「靴が鳴る」に関しては、無理やり強引な解説を導いているにすぎないと思う。本を埋めるために興味を引きそうな解釈を創作しただけのことである。良識ある読者の皆さんが、この様な異説に惑わされることの無いよう望んでやまない。
やはり、「靴が鳴る」は、かつら自身が言っているように〝遠足の歌〟なのである。友達同士、手をつないで歩く野道では、心もはずみ靴も鳴るのである。決して、戦争賛歌の童謡ではないのである。中には、靴の音といえば軍靴を思い出す人もいようが、かつらの思い描いたのは子供たちの履いた靴、そこから感じた心に響く音、胸を弾ませた音ではなかったか。