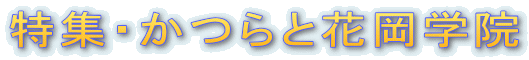
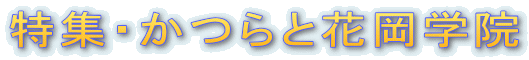
特集の第1回は、練馬区土支田にあった花岡学院とかつらの関わりを紹介します。
 東武東上線成増駅南口、又は地下鉄有楽町線営団成増駅1番出口を出て、川越街道を和光市方面に約300m程下り住宅展示場手前のバス通りを南に約800m程歩くと牛房(ごぼう)の交差点がある。その斜め左側の丘陵地帯(現在、光が丘公園入口と住宅地)に約12,000坪の山野に花岡学院があった。
東武東上線成増駅南口、又は地下鉄有楽町線営団成増駅1番出口を出て、川越街道を和光市方面に約300m程下り住宅展示場手前のバス通りを南に約800m程歩くと牛房(ごぼう)の交差点がある。その斜め左側の丘陵地帯(現在、光が丘公園入口と住宅地)に約12,000坪の山野に花岡学院があった。
当時は、敷地東端の正面入口を入ると、大きな赤松・くぬぎ・欅・その他の雑木林が生い茂り、通称〝ささやきの小径〟を通り抜けると急に視界が広がり、睡蓮の花咲く小さな池がある。池からの小川に沿って歩くと、右手に大きなすべり台のある〝スタコラ山〟、左手に"瓶の芝生"、その先に広い運動場があった。その側に池からの湧き水を利用した25mのプール、天井ガラス張りの雨天体操場、さらに道路を隔てて木造2階建ての寄宿舎があった。脇の高台には、大変モダンな集中暖房を備えたスレート葺き平屋建の洋館建築、学院本部と教室のある本館があった。
健康を充分管理しながら、勉強も出来るという日本最初の私立の林間学校である。医者の道に進まず夢多き文学青年であった子息花岡忠男のために〝ペスタロッチ教育〟を教育方針として、開業医であった父和雄が大正14年に創立した。
広大な敷地であったが、生徒は少なく最初は一人だった。昭和3年度の入学生徒は3名、在校生10名、卒業生2名であった。生徒の体質や学習程度に応じた個人教育でもあったから、優秀な生徒は卒業後、暁星・雙葉・早稲田・成城等の一流校に進学していた。花岡和雄は私財を投じて運営にあたっていたが、生徒が少ないことから学費の高いことは止むを得ず、サラリーマンの月給が20数円であった時代、花岡学院の月謝は30円だった。従って、学院の生徒は裕福な家庭の子女も多く、大臣や外交官の子弟もいた。
かつらが正式に、花岡学院で子供達の作文や詩の指導についたのは、昭和8年であった。型にはまった普通の学校には見られない自由な空気があり、健康的にも精神的にも、のびやかな教育が行われていた。授業も教室の中だけでなく、広い敷地の木陰で行うなど、自然環境を充分生かした教育だった。学院の運営には和雄の長男忠男があたったが、まだ若く、大正デモクラシーで育ったロマン豊かな文学青年で、その友人達も新進気鋭の好青年が多かった。
 かつらは和服の着流しで白子の家から通っていたが、時には、きちんと背広を着て来ることもあった。花岡学院では、主に〝詩や文学〟を教えており、時には児童と一緒に「靴が鳴る」や「雀の学校」を歌ったり、運動会ではパン食い競走に参加したり、洗面器に顔をつけ、誰が一番長くつけていられるか競争したりもした。
かつらは和服の着流しで白子の家から通っていたが、時には、きちんと背広を着て来ることもあった。花岡学院では、主に〝詩や文学〟を教えており、時には児童と一緒に「靴が鳴る」や「雀の学校」を歌ったり、運動会ではパン食い競走に参加したり、洗面器に顔をつけ、誰が一番長くつけていられるか競争したりもした。
父兄を迎えて、音楽会や水泳大会を催すこともあり、音楽会などで興に乗ると、かつらは舞台に上がって、歌声に合わせて軽快に踊ることもあった。
右の写真は、左端が花岡忠男、右から2番目がかつら。
元々、花岡学院は、文部省令に従った政府から認可された小学校であるから、資格のある教員のほかに、かつらのように花岡忠男主事の友人知人を講師として招いていたので、教育の内容も他の小学校とは異なり、かなりユニークで、しかも個人の個性を尊重し、のびのびと学習していた。討論会を開き、課題について自由に発言させ、相手の意見を良く聞くことを教えたり、必ずしも勉強が得意でない子供にも発言の機会を作るなど、各人の意見を自由に言わせていた。時には、学院の卒業生が来て指導に当たったり、グループを作らせ、生徒自らの企画で芝居をさせたりもした。
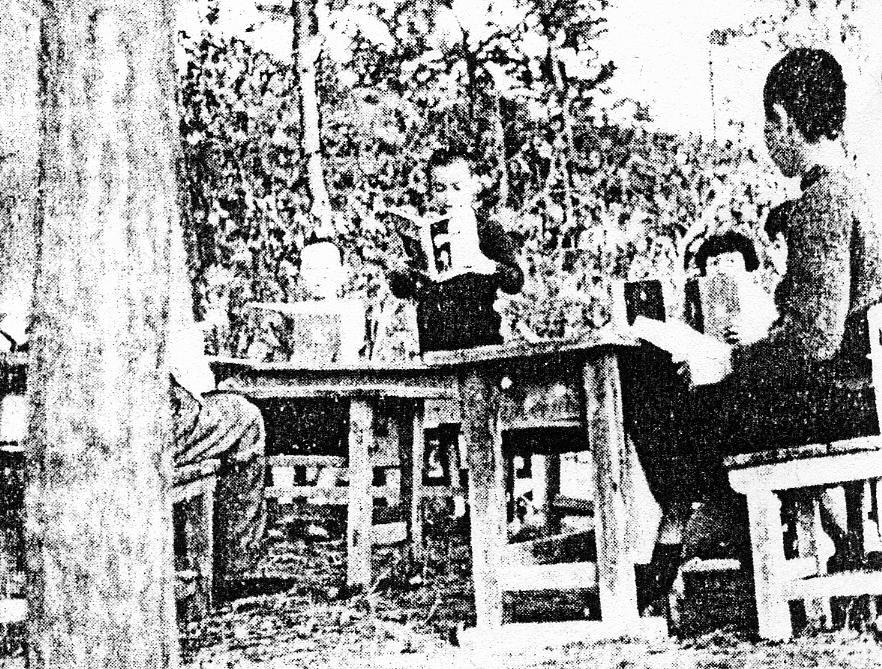 日曜郊外学校や夏の林間学校なども開催され、学院内でも色々な行事が行われたが、かつらも好んでそれに参加し、生徒の詩文に赤インキの細かいペン字で添削したり、やさしい言葉で誉めることが多かった。かつらは次のようにアドバイスしている。
日曜郊外学校や夏の林間学校なども開催され、学院内でも色々な行事が行われたが、かつらも好んでそれに参加し、生徒の詩文に赤インキの細かいペン字で添削したり、やさしい言葉で誉めることが多かった。かつらは次のようにアドバイスしている。
「すなおにまわりのものを見つめて、そのままうつしとると詩になるんですよ」
児童の誌文を集めた「おひさま読本」が、かつらの指導で発行された。ガリ版刷りの薄い冊子であったが、花岡学院の生活を物語っている。昭和10年には花岡学院の機関誌「楽園」が児童文化社から発行され、かつらは童謡を寄稿している。第4号から、清水桂の本名で編集兼発行人を務めた。
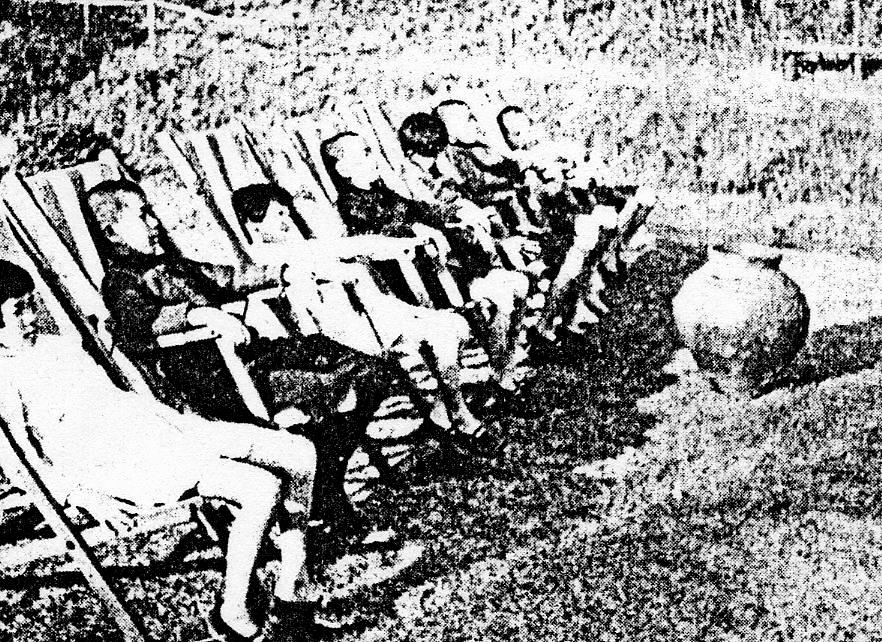
学院の自然環境の中でのびやかに育つ元気な子供や、寄宿舎生活の寂しさの見える子供達を見て詩情を深め、学院のために生活の歌を作詞した。
寄宿舎で眠りにつく時歌われた「おやすみの歌」と学校行事や屋外での運動会などで歌われた「国旗あげの歌」「国旗おろしの歌」である。
当時、生徒や卒業生がかつらを慕って白子の自宅を訪ねると、いつも小箱に入ったお菓子を頂いたがそれを楽しみにしていた生徒もいて、今でもそのことを懐かしがっている学院の卒業生もいる。
花岡忠男の弟孝雄は学務を手伝っており、その弟で当時学生だった信男も学業の休みの折には何くれとなく手伝ったり遊びに来たりして、二人ともかつらに優しい兄貴のような親しみを感じていた。卒業後、信男は神田にあった父の病院に医師として勤務し、花岡学院の健康診断や健康管理にも従事していたので、月に数回はかつらと逢うことがあった。
「常に背広をきちんと着ておられ、温顔は一度会えば忘れられないような暖かさで、児童に対するやさしさを、そばにいる私達にも感じさせる、その人柄は忘れることは出来ません」
 花岡信男は神田栄町の生まれで、かつらの生まれた深川とも近かったから親近感があった。「深川は粋なところが多かった。そのような下地もあって、かつらさんは端正なお姿であったのかも知れません。背が高くすらりとしたひとでした。学院からの帰り道、かつらさんと一緒に子供たちと手をつなぎ「靴が鳴る」や「夕焼小焼け」を歌いながら歩いたことが思い出されます。川越街道から成増駅は見通せて、汽車に遅れそうになっても皆で遠くから手を振りながら大声で”汽車 待て”と叫ぶと、駅長さんがおろおろして発車の合図の笛を鳴らさずに待っていてくれた。そんな、のんびりした時代でした」と述懐している。
花岡信男は神田栄町の生まれで、かつらの生まれた深川とも近かったから親近感があった。「深川は粋なところが多かった。そのような下地もあって、かつらさんは端正なお姿であったのかも知れません。背が高くすらりとしたひとでした。学院からの帰り道、かつらさんと一緒に子供たちと手をつなぎ「靴が鳴る」や「夕焼小焼け」を歌いながら歩いたことが思い出されます。川越街道から成増駅は見通せて、汽車に遅れそうになっても皆で遠くから手を振りながら大声で”汽車 待て”と叫ぶと、駅長さんがおろおろして発車の合図の笛を鳴らさずに待っていてくれた。そんな、のんびりした時代でした」と述懐している。
日支事変から戦時色が強まり、物資も不足して学校の運営も滞りがちとなったが、神田区では養護施設設立の気運があった。そこで、学院は全施設を神田区に寄付することにし、かつらの関係はとぎれてしまった。しかし、忠男とかつらは酒が好物で酒席でのお付き合いは続いていた。
花岡学院は武蔵健児学園として再出発したが、昭和20年に閉鎖されてしまった。戦後、この辺りは米軍に接収されてグラントハイツとなり、現在は光が丘公園の一部になっている。
特集制作にあたり、花岡信男先生にご指導ご協力を頂きました。
![]()